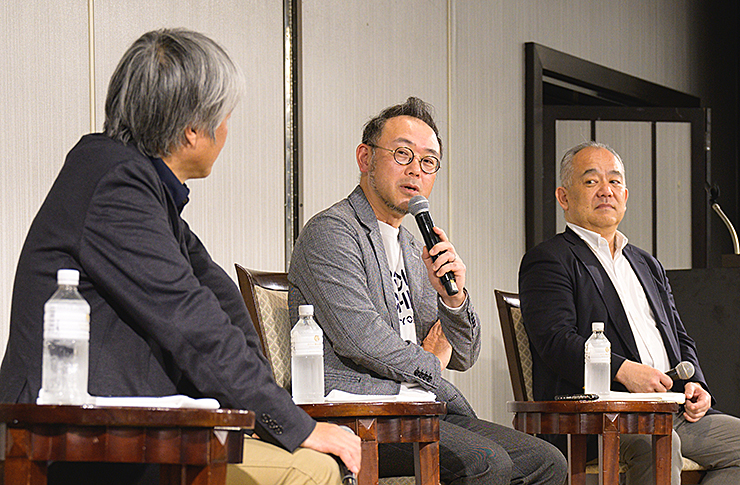中期経営計画の策定(前編:意義とプロセス)/山下 厚
2025.08.18 COLUMN
#ビジネス戦略#新規事業
中期経営計画の策定プロセス
次に、中期経営計画の策定プロセスについて述べていく。究極的には、自社にとって最適な進め方を模索すれば良いのだが、オーソドックスな進め方として、参考になれば幸いである。
まず、企業や事業としての「目指す姿」について、定量と定性の両面で定義することが出発点となる。定量とは、売上高や営業利益などの目標値の設定だ。例えば、現状の自社の売上高が100億円だとしよう。3年後または5年後に120億円を目指すのか、150億円を目指すのか、200億円を目指すのか。初期の段階で概算レベルの目線は揃えておく必要がある。
一方、定性とは、自社の市場における存在意義や提供価値の中身の話である。自社や自事業は、3年後や5年後、どのような姿であるべきか。大海原の真ん中に身を置く今、あらゆる方向へと進む可能性が考えられるはずだ。ブレインストーミング形式でテーブルの上に意見を並べていくのも良いが、白紙から「目指す姿」を固めていくのは難しい。そのため、「目指す姿」を思考する上でのインプットとする意味でも、序盤の段階で外部環境や内部環境の分析に着手することが一般的である。
次に、環境分析の結果から、あるいは並行させる形で、検討すべき大きなテーマの項目出しを行う。リスト形式で一覧化させるイメージだ。幅広く事業を展開する大企業においては、いわゆるコーポレート全体として採るべき戦略や、基盤のあり方に関するテーマから検討の俎上に挙げていく。
なお、この段階では、進め方がわからず、いわば手探り状態のメンバーが一定数いるものである。そのため、検討を軌道に乗せていくためにも、社内関係者を力強く主導していく役割(チーム)は明確にした方が良い。一般的には、経営戦略や経営企画を管掌する部門が担うことが多いが、推進力の発揮という点で、コンサルティング支援のニーズも大きい。当社でも支援実績が豊富な局面である。
コーポレートとしての戦略や基盤についてテーマが出揃った段階で、あるいは、検討自体が一定進捗した段階で、各事業部門内での検討もスタートする。コーポレートの各テーマおよび方針と整合させる形で、個別の事業や組織としての施策出しへと繋げていく。事業や組織を跨るイシューについては、所属関係なく適任者をアサインした分科会を発足し、協議を重ねていくこともある。関係者が一同に会し、合宿のような形で集中的に討議することも効果的だ。
各事業部門内での施策出しまで進められたら、いよいよ詳細な数値計画へと落とし込んでいく。初期的に定めた売上高や営業利益などの概算の目標値を精緻化していく。
こうして、定量と定性の両面で精査がある程度進んだ段階で、然るべき社内レビューを実施する。中間レビューと最終レビューの2段階に分けても良い。また、各事業部門内に閉じたレビューとは別枠で、全社の観点からチェックする趣旨のコーポレートレビューを開催することもある。その後、各レビュー内で示された意見を取り込み、画竜点睛まで仕上げ、最終的なFIXを迎える。ここまでの各プロセスを丁寧に進めていくと、トータルでは、最低でも6か月程度を要する。中期経営計画の策定とは、全社を挙げての一大プロジェクトなのである。
本稿はここまでとし、次回は<中編>として、中期経営計画を策定していく上での実務的なポイントを詳述していく。
<中編>は、以下からお読みいただけます。
中期経営計画の策定(中編:実践上のポイント 環境分析編)/山下 厚

山下 厚Atsushi Yamashita
スカイライト コンサルティング株式会社 ディレクター
東京大学法学部法律学科を経て、2009年にスカイライトコンサルティングに参画。主にBtoC企業を対象とする戦略策定、企画立案から実行推進までをワンストップに手掛ける「ビジネス戦略ユニット」の統括責任者。
デジタルマーケティング領域の知見者として、特に消費者の生活に関わる各種業界・業種において、企業全体の戦略見直しから新規事業・サービスの立上げまで幅広く手掛ける。上場企業向けの新規WEBメディア立上げや、ECサイトリニューアル等、自らがPMとして舵取りをして実現まで成果を導いた案件も多数あり、プロジェクトマネジメント有識者として中小企業の外部講師としても登壇。
出資および買収案件における事業デューデリジェンスも得意とし、複数企業間の協業モデル構築に関する知見および実績がある。また新規事業として、マーケティング知見のアジア展開もリードする。