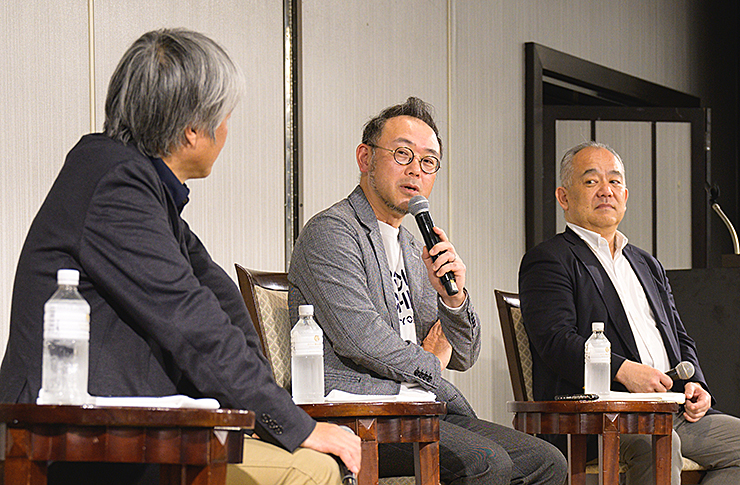中期経営計画の策定(前編:意義とプロセス)/山下 厚
2025.08.18 COLUMN
#ビジネス戦略#新規事業
中期経営計画の意義
中期経営計画と聞くと、現場で業務に従事されている人には馴染みの薄い言葉かもしれない。むしろ、日々意識する計画といえば、年次で策定する事業計画だろう。中期経営計画とは、その年次の事業計画よりも、遠い未来まで見据えた上で構想し、計画に落とし込んだものである。期間としては、3か年での計画が一般的だが、最近では5か年で計画する企業も珍しくない。そして、3か年の計画を策定するためには、少なくとも5年先、場合によっては10年先までを展望する視野が必要となる。こう書くと、「ここまで競争環境が激化している時代に、遠い先の未来は予想のしようがない」という意見も出てくるかもしれない。
しかし、敢えて強調したいのは、決められた未来を計画書に落とし込むのであれば、中期経営計画の必要性は限りなく薄いということだ。むしろ、未来の予想が困難な時代だからこそ、企業としての船旅の方向をしっかりと定義することに意義がある。リスクや脅威にも目を向ける一方で、アップサイドとしての大いなるポテンシャルも秘めている。さて、自社および自事業は、この先どこへ向かうべきなのか。中期経営計画の策定は、決して単純作業には落とし込めない、未来への探索行為そのものなのだ。
実際、日々の事業運営の中で、腰を据えて自社の未来に思いを馳せる時間はあるだろうか。自社の社会的意義や世の中に対する提供価値について、じっくりと語り合う機会もそう多くないのではないか。中期経営計画の策定というプロセスの中で、「5年先や10年先、こうなっていると良い」という白熱した議論が展開されていくこと自体、ポジティブな意味合いを持つものである。
このような時代であっても、未来を読む手掛かりが何もないわけではない。確かに、短期的な社会情勢の変化に左右されてしまうと、進むべき方向が定まらないという感覚に陥るのも無理はないだろう。例えば、生成AIの劇的な進化や、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、トランプ米大統領の関税問題などは、3年前には予想し得なかったはずだ。また、人々の生活や働き方に多大なる影響を与えた新型コロナウィルス感染症の流行も同様である。しかし、10年や20年という視野で遠い未来を展望すると、日本国内においては、労働人口の減少や超高齢社会への移行は確実に進んでいく。結果、企業における「人手不足」の問題は深刻化の一途を辿るだろう。その一方で、生成AIを含むデジタルテクノロジーの活用によって「足りない人手をどう補うか」という意識は一層高まっていくはずだ。グローバルに目を向ければ、アジアやアフリカを中心に人口は幾何級数的に増加している。地球上の限りあるエネルギー資源や食料資源の危機に関しては、世界全体として向き合い続けるべき問題である。

中期経営計画の策定は、そうした国や産業全体に係る長期的なトレンドも勘案した上で、意思を持って「未来にこのようなピンを立てる」というある種の覚悟でもある。激動の時代を力強く生き抜くために、自社や自事業の「目指す姿」を定義することは、大変高尚な試みなのである。
さらにいえば、中期経営計画は、遠い未来のシミュレーションという側面も帯びている。敢えて大胆な仮定を置き、短期的には起こり得ない極端なシナリオを検証することも有効なアプローチだ。例えば、「遠い未来に、自社の従業員がこれまで提供してきた価値はAIに完全に代替されてしまう」と仮定した場合、自社や自事業は、何をせねばならないのか。「宇宙開発が進み、月面が地球とはほぼ地続きの市場になる」等という仮定を置いて思考を重ねるのも良いかもしれない。あらゆるシナリオを検証し、遠い未来に備えておくことで、予想もし得なかったような有事の際にも慌てずに対処できるというものだ。
加えて、特に上場企業の場合は、自社の外側にいるステークホルダーに対する情報開示という観点があることも忘れてはならない。「自社の方向性を示すこと」は、株主にとって大きな関心事である。「今後に期待できそうな計画か」という視点で冷静に見ると、株式市場の反応とも一定程度リンクすることを実感できる。
また、「中期的な自社または自事業の注力領域・度合を示すこと」は、取引先やパートナー企業に対してもメッセージ性を帯びる。領域的に密接に関係する取引先の目線では、その注力度合の明示を受けて、ある種の安心感が醸成されるだろう。それは、取引先との信頼関係の維持や発展にも寄与し得るものだ。パートナー企業の目線でも、「この領域で抜本的に協業していく可能性を模索しよう」という具合に、アライアンスの検討材料にもなり得るものである。
次ページ)中期経営計画の策定プロセス